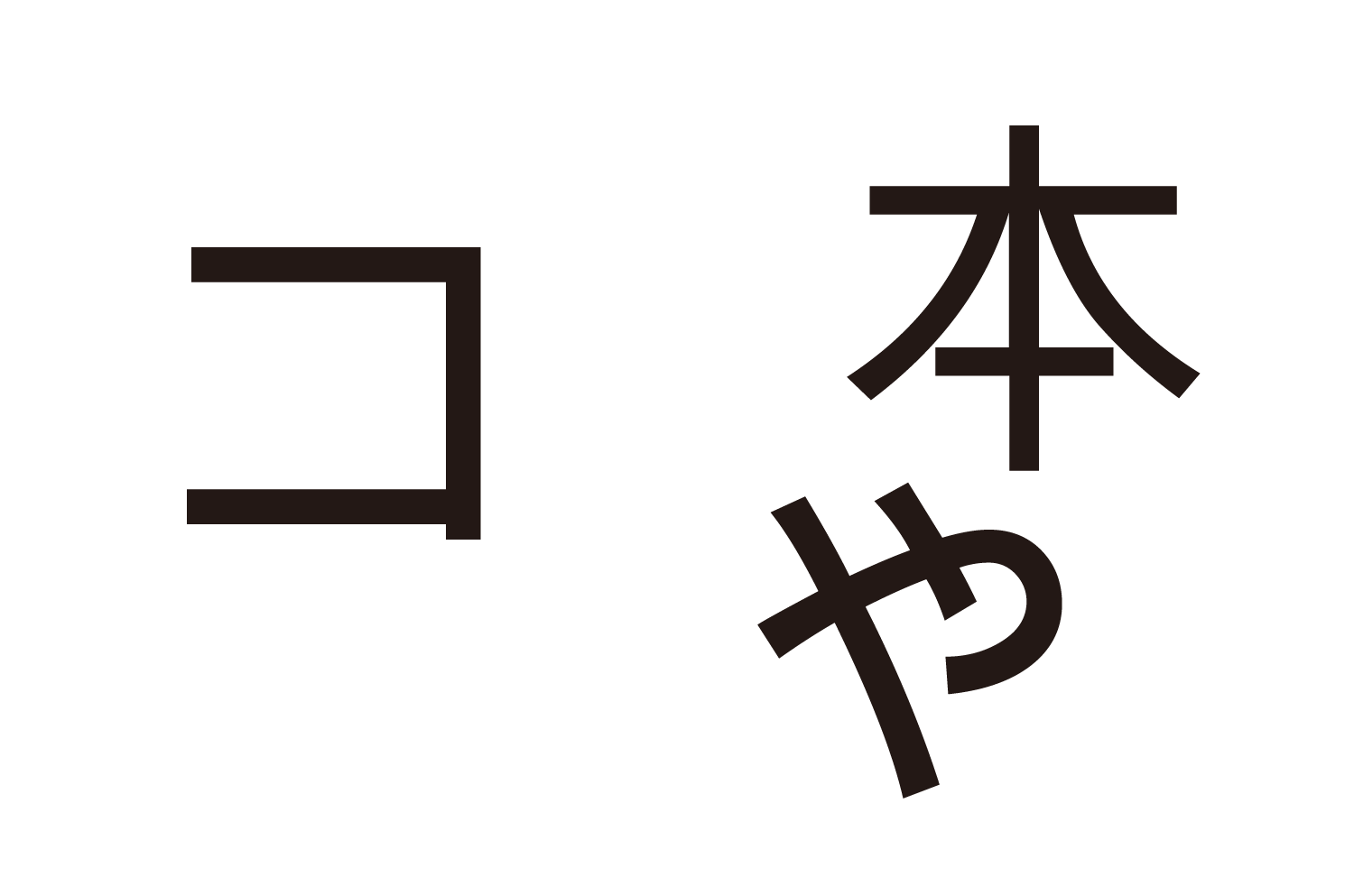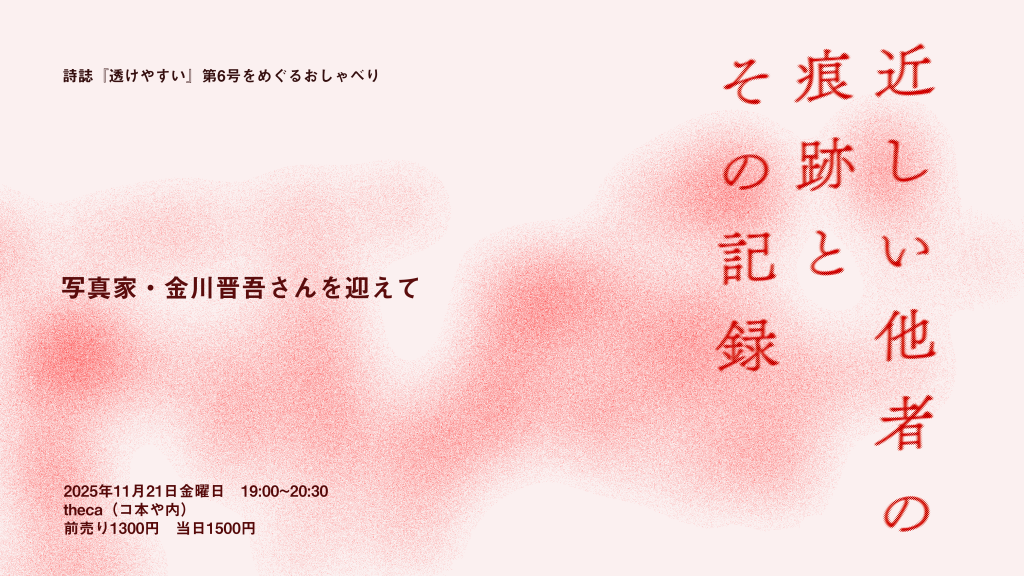
詩誌『透けやすい』第6号をめぐるおしゃべり
近しい他者の痕跡とその記録:写真家・金川晋吾さんを迎えて
日時:2025年11月21日(金) 19:00-20:30 (開場18:30)
会場: theca(コ本や内) 東京都新宿区山吹町294 小久保ビル2階
料金:1300円(前売)、1500円(当日)
チケットURL:https://coubic.com/sukeyasui/1490671
主催・企画:透けやすい
詩誌『透けやすい』では第六号「透けやすい通り道」を出発点に、写真家・金川晋吾さんを迎えてトークイベントを開催します。
第六号の企画「かつてあったものたちへ」では、詩人たちの記憶に残る場所や近しい人々について、喪失の予感を抱きつつ言葉をもって対峙することを試みました。きわめて私的かつ日常的な関係を、どのように記録し、表現しうるのか?失われつつある風景の痕跡を、どのようにとどめることができるか?
本イベントでは、父や同居人など親しい他者を写真に撮り続けてきた金川晋吾さんとともに、これらの問いに向き合います。
写真と詩という異なる媒体を通じて、さまざまな関係の写しかたを考える夜。
みなさまのご参加をお待ちしています。
【習慣はスムーズに変化していき、そこに劇的さが無いのは、自分たちの日常の平穏さを守っているためなのかもしれなかった。わたしたちはいつも、少し経ったあとで(落ち着いたころにまた会いましょう、と約束を交わすくらいの間合いで)習慣と習慣の結び目に意識を向けて、かつてそこにあったものと、そこにいた人々のことを思い出してみるのだ。
『透けやすい』は二〇〇〇年くらいに産まれて、二〇二三年くらいに第一詩集を出した詩人の集まりで、今号で第六号になる。二〇二三年とか二〇二四年くらいに大学の学部や、大学院を卒業した『透けやすい』の詩人たちは、二〇二五年夏の昼過ぎ、幡ヶ谷のカフェで気がついたら「もう行くことがなくなった場所/近い将来に行くことがなくなるであろう場所」についての話をしていた。それは親の車の後部座席に乗せられていく祖父母の家であったり、通っていた小学校だったり、家族旅行でよく訪れる場所であったりした。
よだれかけに付着した唾や、ツツジの花の蜜、夕方の無責任なまどろみの匂いがするこれらの場所のことを自然と思い出したのは、たぶんわたしたちの幼さが「落ち着いたころ」だからだ。万能に見える両親や、幼さを包み込んでくれるような祖父母はもうおらず、完璧ではない両親と、老いていろいろなことを忘れていく祖父母の輪郭が眼の前にはある。
目的地へと向かう道、通り道はその目的地がすっかり習慣にとけこんでいる場合にはほとんど意識されることがない。「通り道」と口に出すときは多くの場合が、「通り道だった」と言っている気がする。それは例えば、同行者から見るといまの生活には馴染みがないように見える地域ですいすいと穴場の喫茶店に入店していくとき。「どうしてこんなところ知っているの?」と聞かれたあなたは「前に行っていた美容院までの通り道だったから」と答えるだろう。
習慣から消え去っても、通り道、その痕跡は確実に身体に刻みこまれている。そして、ふとした日常の裂け目で顔を出す。幼い日を思い出してみるこの日々も、また通り道になる。落ち着いたころにいつでもみんなに会えるように、今号ではきちんと上手に思い出す練習をしてみたい。】
透けやすい第6号『透けやすい通り道』はじめに―通り道だったと気がつく(川窪亜都)
【登壇者プロフィール】
透けやすい
2023年結成。今宿未悠、川窪亜都、田村奏天、源川まり子の若手詩人4名による詩の雑誌。第一詩集を出版するタイミングで創刊した同人誌で、それぞれの詩がどうしてか「透けやすい」ことから名付けられた。研究・パフォーマンス・俳句・出版編集などのバックグラウンドをもつメンバーが、現代詩のさらなる可能性をひらいていくための空間である。
金川晋吾
写真家。1981年京都府生まれ。父や伯母という身近な他者や、婚姻や血縁で結ばれていない他者との共同生活を題材に、写真と言葉を通して、人間の分からなさや自己と他者の関係のあり方を問い続けている。2016年『father』(青幻舎)、2021年『犬たちの状態』(太田靖久との共著、フィルムアート社)、2023年『長い間』(ナナルイ)、『いなくなっていない父』(晶文社)、2024年『明るくていい部屋』(ふげん社)、『祈り/長崎』(書肆九十九)刊行。近年の主な展覧会に2022年「六本木クロッシング2022展:往来オーライ!」森美術館、2024年「現在地のまなざし 日本の新進作家 vol.21」東京都写真美術館など。2025年11月1日より国立国際美術館で開催のグループ展「プラカードのために」に参加。